概要予約周辺レビュー特典を獲得詳細おすすめ
シェア
旧首里城守礼門
Shureimon3.0
79件の口コミ
 レビュー:437件
レビュー:437件24時間年中無休
オススメの滞在時間:10分
所在地:
日本、〒903-0826 沖縄県那覇市首里金城町1丁目7−1地図
電話番号:+81 98-886-2020
旅行者の声:
それはまた非常に美しいことができます、中国語は実際にはアーチです。第二次世界大戦の後、それはアーチが残っていると言われました。古代中国の使者を迎えた場所です。アーチには、礼儀の国のプレートが飾られています。以前にいくつかのプレートを変えたようです。名前は異なるでしょう。天朝と比べるな、琉球らしい鳥居だ。
表示11名がお気に入りに追加
旧首里城守礼門のハイライト
一部の情報はGoogle翻訳によって翻訳された可能性があります
2000年に世界遺産に登録された守礼門は、2,000円紙幣の裏側の文様であり、沖縄の文化的象徴です。多くの自然災害や人為的災害が発生した後も、守礼門の鳥居は今日も明るく輝いています。赤い色と優雅な気質は、沖縄の人々が楽観的で無関心であることを人々に伝えているようです。今日まで、沖縄では必見です。 14世紀に建てられた首里城は、権力闘争、戦争爆撃、火災などの理由で何度も焼失し、再建されました。正門「中山門」は早くも1908年に破壊され、2番目の門は警備員の門。 1579年、明代の万暦帝は琉球王国のシャンギョン王の称号を授け、「海岸から遠く離れた琉球王国だけが教えを厳守し、世界の義務を修復し、敬意を表して、それは儀式の遵守の状態と呼ばれています。守礼門の名前の由来です。その後、中国が列聖の使者を琉球に送るときはいつでも、琉球の王と役人は使者を見るためにアーチの下で3回お辞儀をしました。
旧首里城守礼門の周辺のおすすめスポット
旧首里城守礼門のレビュー
一部のレビューはGoogle翻訳によるものですレビュー投稿
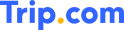 (79件の口コミ)Trip.com
(79件の口コミ)Trip.com (437件の口コミ)TripAdvisor
(437件の口コミ)TripAdvisor/5
とても良い件の口コミ全て (79)
最近のレビュー
画像付き (39)
高評価 (71)
低評価 (1)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 16
旧首里城守礼門のよくある質問
追加情報
その他のおすすめ
首里城
6.0
4.5/5787件の口コミ
372円
首里城公園
6.0
4.6/5175件の口コミ
372円
沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー)
5.1
4.5/5151件の口コミ
沖縄美ら海水族館
6.8
4.8/51581件の口コミ
162円オフ
2,018円
周辺の観光スポット
国際通り | 首里城 | 首里城公園 | 波上宮 | 沖縄県立博物館・美術館(おきみゅー) | 波の上ビーチ | 牧志公設市場 | Orca 水中観光船 | 福州園 | 慶良間諸島ダイビング体験 | 旧海軍司令部壕 | 美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジ | 沖縄こどもの国Okinawa Zoo & Museum | 市場本通り | 琉球村 | 沖縄県営奥武山公園 | 壺屋やちむん通り | 識名園 | 玉陵 | おきなわワールド | 沖縄海パラグライダー体験 | 平和通り | 美らヤシパークオキナワ・東南植物楽園 | 国際通り屋台村 | 金城町石畳道 | シネマQ | 沖縄県庁 | てんぶす那覇 | 琉球八社 沖宮 | ストリートカート 沖縄
那覇の人気観光スポットの種類
那覇のおすすめレストラン
もとぶ牧場 那覇店 | Okinawa Tonkatsu Shokudo Shimabutaya Kumoji | グランドキャッスル カフェ&ダイニング | フォンテーヌ | 中国料理 舜天(Shunten) | スチームダイニングしまぶた屋 | Yakiniku Gokujogyu | Nihonryori Fuji Daburutsuri by Hirutonnahashurijoh | ALL DAY DINING vision&emotion | 花笠食堂 | 空港食堂 | 牛皇 | 牛角 おもろまち駅前店 | 目利きの銀次 新都心店 | 沖縄地料理 波照間 国際通り店 | yotsutake | Sakurazaka | Steakhouse 88 Kokusaistreet | ゆうなんぎい | Mion | 我那覇豚肉店(カフーナ旭橋) | 37ステーキハウス&バー那覇 | Pork Tamago Onigiri Honten | 和風亭 那覇メインプレイス店 | 天龍 | やきにく華 | かき小屋 那覇桜坂 | Izumi, ANA Crowne Plaza Okinawa Harborview | てんtoてん | 神戸 Bar 仲々
人気の都市
人気目的地のおすすめ観光スポット
周辺のソウルの観光スポット | 周辺の東京の観光スポット | 周辺の大阪の観光スポット | 周辺の福岡の観光スポット | 周辺のバンコクの観光スポット | 周辺の名古屋の観光スポット | 周辺の札幌の観光スポット | 周辺の台北の観光スポット | 周辺の沖縄の観光スポット | 周辺の釜山の観光スポット | 周辺のマニラの観光スポット | 周辺の香港の観光スポット | 周辺の上海の観光スポット | 周辺のホーチミンの観光スポット | 周辺のハノイの観光スポット | 周辺のバリ島の観光スポット | 周辺のロサンゼルスの観光スポット | 周辺のシンガポールの観光スポット | 周辺のクアラルンプールの観光スポット | 周辺の横浜の観光スポット | 周辺のホノルルの観光スポット | 周辺の広島の観光スポット | 周辺の京都の観光スポット | 周辺のセブの観光スポット | 周辺の仙台の観光スポット | 周辺の那覇の観光スポット | 周辺のパリの観光スポット | 周辺の仁川の観光スポット | 周辺のロンドンの観光スポット | 周辺のダナンの観光スポット
人気のランキングリスト
カスキ周辺の人気豪華なホテル | カーブレ・パランチョーク郡周辺の人気豪華なホテル | バンコクの人気高級レストラン | Gokarneshwor周辺の人気豪華なホテル | 威遠周辺の人気家族連れにおすすめ | 長春のバー おすすめ6選 | 連平周辺の人気家族連れにおすすめ | 上海の人気高級レストラン | モスクワのクラブ おすすめ12選 | 成都の高級レストラン おすすめ23選 | 鄭州の高級レストラン おすすめ6選 | ブリュッセルのバー おすすめ9選 | ランデリ周辺の人気豪華なホテル | 盤錦のラグジュアリーホテル おすすめ4選 | ヴェネツィアの高級レストラン おすすめ15選 | 五台の人気ラグジュアリーホテル | 欒川周辺の人気家族連れにおすすめ | 愛媛県の人気豪華なホテル | 農安周辺の人気家族連れにおすすめ | 三江周辺の人気家族連れにおすすめ | 東京の夜の観光スポット おすすめ19選 | ソウルの夜の観光スポット おすすめ11選 | バンコクの夜の観光スポット おすすめ10選 | 重慶の夜の観光スポット おすすめ12選 | 南京の夜の観光スポット おすすめ5選 | 長沙の夜の観光スポット おすすめ5選 | 広州の夜の観光スポット おすすめ6選 | 三亜の夜の観光スポット おすすめ14選 | 上海の夜の観光スポット おすすめ12選 | 西安の夜の観光スポット おすすめ9選
人気のTripメモリー
【沖縄】沖縄で南アフリカ?なカフェ | 【沖縄】那覇でおしゃれホテルステイならここ♡ | 【沖縄/那覇】海とアートを満喫できる唯一無二のホテル🐬 | Tsuboya Yachimun Street 壺屋やちむん通り | 【沖縄】滝のある中国式庭園⭐福州園⭐ | 【那覇】崖の上に鎮座する恋愛成就のパワースポット!波上宮⛩ | 【沖縄】雨の日の沖縄観光にもおすすめ☔️サンゴ染め体験! | 一人でレンタカーを借りずに、週末2日間で沖縄を満喫する攻略 | 【那覇/国際通り】占いしながらめちゃくちゃ可愛いスムージーが飲める🌺🥤 | 【沖縄】レトロな空気が流れるカフェ『コーヒーシャープ ララミー』 | 【沖縄】珊瑚礁の上に建つ、シーサーが守る『波上宮』 | 【今しか見れない景色★】首里城 | 【沖縄】クラシックを聴きながらのカフェタイム | 【沖縄】首里城近くのローカルにも人気のカフェ | 春の沖縄旅行🌸首里城公園は行くべき✨ | 【沖縄】まるで中国?那覇市にある庭園 | 【沖縄/那覇】国際通りごはん🍴きち屋。 | 【沖縄/那覇】国際通りごはん🍴︎久茂地文庫 | 沖縄〜那覇から始める大人女子弾丸旅〜車なくてもOK❗️ | 末吉公園。 | 【那覇で泊まるならココ🌺美栄橋すぐのシティホテル】 | 【沖縄】那覇インフィニティプールから市内を一望 | 敷金苑。 | 愛達魔都初体験 | 【沖縄】国際通りからすぐなのに出たくなくなるホテル!グランコンソルト那覇 | 【沖縄】国際通りにある洗練されたおしゃれホテル🏨 | 【沖繩】波上宮:崖上の神社。 | 沖縄旅行 波の上神宮 | 【沖縄県・那覇市】朝の国際通りを西から東に自転車で駆け抜けました | 【沖縄】サムギョプサル食べ放題!韓国焼肉屋さん
那覇の他のおすすめ体験
日本esim 日数別プラン/データ量別プラン 日数自由選択 カードの受取不要 QRコード | 日本 esim (DOCOMO)トラフィックパッケージ日数利用可能 カードの回収は不要 QRコード | 沖縄+古宇利島+万座毛 1日ツアー【美ら海水族館・熱帯植物園・アメリカンビレッジ・中国語・英語・韓国語・日本語音声ガイド】 | 沖縄県那覇市の沖縄美ら海水族館への日帰りツアー【プライベートカスタマイズチャーターカーがお客様のご要望に合わせてリーズナブルな旅程をご提案・日本人ドライバー+中国人接客】 | 沖縄体験海釣り半日ツアー/那覇発 未経験者も参加可能 | 沖縄美ら海水族館+古宇利大橋+万座毛+琉球村+瀬長島 沖縄県日帰りツアー [沖縄チャーターカー日帰りツアー丨南部丨中部丨北部プライベートカーツアー] | 沖縄県那覇市渡嘉敷島日帰りツアー【沖縄渡嘉敷島日帰り海水浴ツアー(離島港からビーチまでの送迎含む)】 | 沖縄那覇空港モノレールゆいレール電子乗車券1日乗車券 | 沖縄・慶良間諸島日帰り旅行【シュノーケリング+神秘のウミガメ探検+ウォータースポーツ+無人島巡り】 | 沖縄空港送迎|那覇港|OKAポイントツーポイント送迎 | 沖縄美ら海水族館 + 万座毛 + 古宇利島 + アメリカンビレッジ 1日ツアー 【水族館入場券+ 中国語ガイド+ 快適な車+ 買い物なしで楽しむだけ】 | 沖縄万座毛+琉球村日帰りツアー[貸切ツアー、旅程カスタマイズ、中国語/日本語ドライバーオプション] | 沖縄県那覇市の沖縄美ら海水族館への日帰りツアー[那覇への日帰りツアー[グリーン普通車貸切・島内送迎・自由オーダーメイド旅程]] | 沖縄県那覇市の沖縄美ら海水族館への日帰りツアー【沖縄本島プライベートカスタマイズチャーターツアー、ゴールド免許日本人プロドライバー+中国人カスタマーサービス】 | 沖縄 天然温泉さしきの 猿人の湯 | 沖縄体験海釣り半日ツアー/那覇・北谷発+気軽に海釣りの楽しさを体験 | 沖縄 ラド観光 沖縄営業所 | 日本 沖縄 万座毛 + 名護パイナップル園 + 海洋博公園 + 壺屋やきもん美術館 + 国際通り 1 日ツアー [¥ アトラクションはオプション、旅程はカスタマイズ、純粋に楽しむ、中国人ドライバー] | 万座毛+古宇利島+沖縄美ら海水族館+アメリカンビレッジ日帰りツアー【沖縄北部厳選バス日帰りツアー|ガイド可・1人から】 | 沖縄 NEWS那覇店 | 沖縄 ダイビングショップ ハイビスカス | 日本 沖縄観光バス 美ら海水族館/おきなわワールド/古宇利ビーチ/アメリカンビレッジ/東南植物園 ランチと音声ガイド 8 件が含まれます | 沖縄美ら海水族館+万座毛日帰りツアー【古宇利大橋・北谷アメリカンビレッジ・海洋博公園・中国語サービス・複数乗船集合場所】 | 沖縄 琉装スタジオ ちゅら美人 | 沖縄 ジョイクリエイト沖縄ティーダ | 日本 + おきなわ世界文化王国 + 玉泉洞窟 + 波之江御殿 + 波之江ビーチ + アメリカンビレッジ 1 日ツアー [洞窟探検、オプションアトラクション、カスタマイズされた旅程、中国人ドライバー¥] | 沖縄県那覇市の那覇空港への半日ツアー[空港送迎 - 沖縄本島全域、プロの日本人ドライバー/中国人カスタマーサービス] | 【沖縄】那覇発|市内無料送迎|慶良間諸島シュノーケリング|体験ダイビング|マリンアクティビティ|海上ヨット|美景の旅 | 沖縄アメリカンビレッジ + 泊港 + 沖縄県立博物館 + 神道中心への日帰りツアー [近代都市日帰りツアー + 中国語を話すドライバー + 専用車送迎 + 旅程調整可能] | 沖縄県那覇市の那覇空港への半日ツアー[空港送迎 - 沖縄本島全域、プロの日本人ドライバー/中国人カスタマーサービス]
Trip.comについて
お支払い方法
パートナー
Copyright © 2024 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. All rights reserved
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
サイト運営:Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
それはまた非常に美しいことができます、中国語は実際にはアーチです。第二次世界大戦の後、それはアーチが残っていると言われました。古代中国の使者を迎えた場所です。アーチには、礼儀の国のプレートが飾られています。以前にいくつかのプレートを変えたようです。名前は異なるでしょう。天朝と比べるな、琉球らしい鳥居だ。
2019.10.31の火災が燃え尽き、この歴史的遺物が再び完全に破壊され、沖縄全体が募金で再建され、15年後に宮殿全体の再生を楽しみにしています!
第二次世界大戦後に正確な仕様と細部で再建された。数世纪以来,无数旅客穿过这些门,虽然实际的城堡在二战中被摧毁,原始城堡的位置在琉球大学的隔壁,但是任何人只要读过或见过马休·培里1850年访问冲绳的照片或报刊都会在里面发现这个门。これらのドアが城の再建を導いたように、これらの写真を見てまた過去に戻ったような気がします。
There are a lot of people, and the place is good. It's quite clean. It feels like the air is good. The architecture mixes the style of Chinese architecture in Tang Dynasty with the traditional method of Ryukyu - "the contrast of red tile and white clay, two prominent roofs, self-stable aesthetic feeling, and hangs the Chinese character plaque of "the state of observing rituals" which can really represent Ryukyu. Scenic spots are free.
Tour Shouli City. It was originally the palace of the Ryukyu Kingdom. It was destroyed by war during World War II. It was restored and reopened in 1958. When entering the ancient city of Shouli, we will first pass through a gatekeeper, which is the only ancient building on the island listed as a world cultural heritage by the United Nations. The four characters on the plaque "State of Observance of Rites" are given by the Chinese emperor.
遠くからでも確認できる朱色の屋根が魅力的です。
The gates are the entrance to Seoul and the first stop of the collection. The red buildings from Fig. 1 to Fig. 6 are free of charge. Tickets are required to enter the red inner hall. There are booklets for collecting stamps in the customer service center outside the gates. Simplified, traditional, Japanese, English and Korean versions are available. There are 25 small and 2 large chapters. If you want to cover them, you have to enter the inner hall and stamp 6 stamps. After collecting, you can exchange gifts at the service center where the booklet is collected. You can also ask the staff to stamp the emperor's stamp for you (see the last picture). Seal stamping is an exceptional excitement!
ここはさすがの雰囲気がありました!